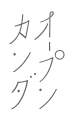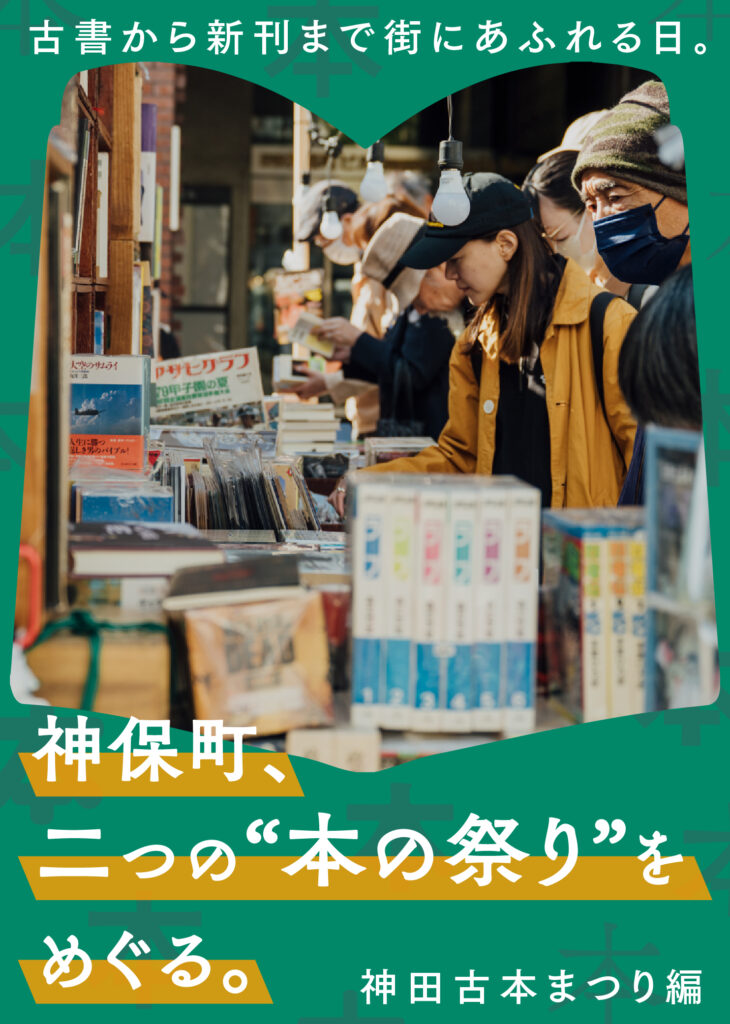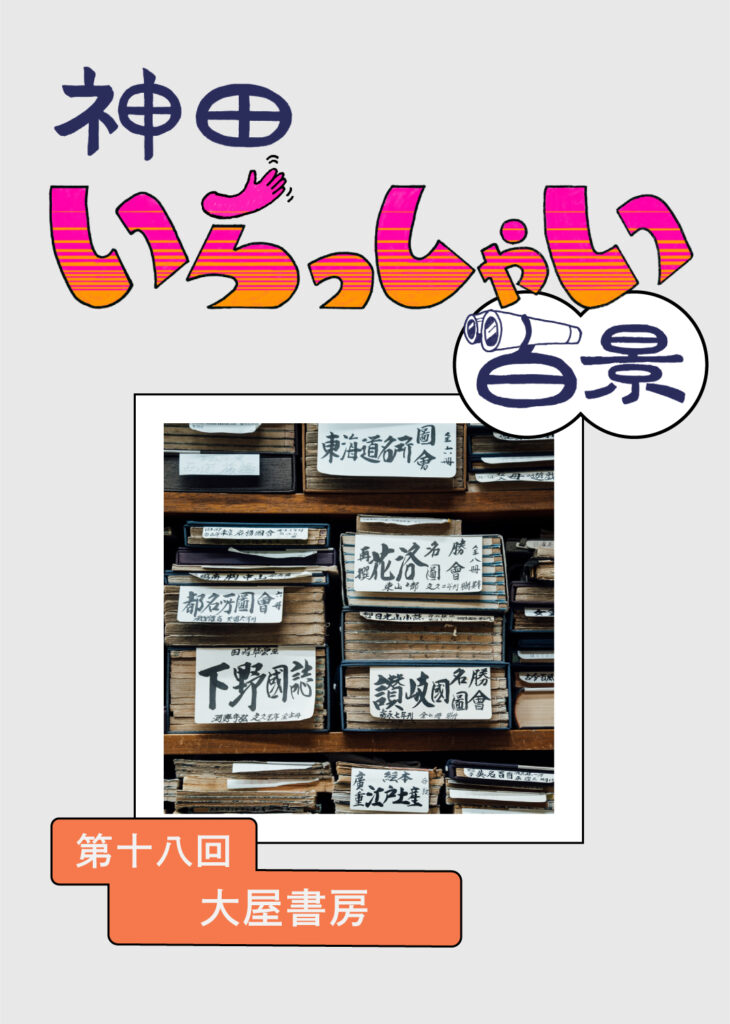神田祭、陰の立役者たち|其の三・神田明神 神職
日本三大祭のひとつとされる神田祭。
壮大な歴史と規模を誇る日本屈指のお祭りですが、そこには、まちの人々の手によって絶やすことなく受け継がれてきたという背景があります。時代とともに、地域に関わる人もまちの形も変わりゆく中で、伝統としてあり続ける神田祭。どういった人たちが、どのようにしてこの日を支えているのでしょうか。
約400年の歴史を持ち、108町会が参加するほどの規模ゆえに、関わる人の数も膨大ですが、その中で中心となって支え続ける「陰の立役者」に密着します。
三人目は、祭礼の主な舞台となる神田明神に仕える「神職」。神田明神がこれまで発展を遂げてきた背景には神職の存在が不可欠ですが、神田祭も同様です。神職が中心となって各氏子地域と連携しながら、神田明神に祀る神様と地域のための祭礼として守り続けています。
多くを語ることはそうないものの、常に地域を見守る神職。神田明神の禰宜として仕えられる岸川雅範さんにお話を伺いました。
〜〜〜〜〜〜〜〜
●神田祭はなぜあるのか

——神田明神は神田祭の中心となる場所で、もっとも注目が集まります。神田明神と神田祭はどういった関係なのでしょうか?
岸川 そもそもなぜ神社があり、お祭りがあるかという話からすると、神様がいるからなんです。神様がいて、その神様が守る地域があり、その地域に住む氏子がいる。いわゆる「氏神氏子」の関係性が根底にあります。
ただ、氏子の方はそれぞれにお仕事や生活があり、神田祭のような規模のお祭りを一から準備してすべてを執り行うことは困難です。そのため、専門の人間である神職が仲執持として代わりにお祭りを行っているんです。今でこそ神田明神は神田祭の中心的な立場で関わっていますが、我々は氏子の皆さんの代役をする、ということが本来の立ち位置になります。
——神田明神のお祭りではなく、地域全体のためのお祭りなんですね。
岸川 そうなんです。神田祭の中に「神幸祭」という神事があり、それは氏子区域の人びとのために神社が主導して行います。神様をお乗せした3基の鳳輦神輿を筆頭とした行列が、すべての氏子区域を清めるために一日かけて約30kmの距離を巡るんです。
神田祭というと、神輿宮入がメインだと思う方も多いですが、神幸祭と神輿宮入の二つが合わさって神田祭なんです。他にも献茶式や例大祭といった神事がありますが、氏子をお祓いして清めること、そしてまちの人たちが神様に対して奉仕すること、この二つが神田祭の大きな目的になります。

——岸川さんご自身はどういったことを担当されるのでしょうか?
岸川 神職何人かに分かれて108の町会を担当し、神田祭に向けた会議に参加したり、お祭りの道具を届けたりと細かなやりとりをします。さらに町会に出向いて神輿神霊入れを行いますが、神輿宮入当日は基本的にまちに出ることはありません。むしろまちのためのお祭りなので、我々は神田明神に宮入する各町会の神輿をしっかりお迎えすることが重要な役割になります。



●神田にある神社だからできること
——宮入はまちの人にとって大きな見せ場でとても盛り上がりますね。一方で、100以上の町会が集まる唯一の場所なので運営面での苦労がありそうです。準備はどのように進められるのでしょうか?
岸川 前年に祭典委員会というものが立ち上がり、そこから大きな方針の話し合いを始めます。御神輿担ぎは車道を使用するので警察や消防の方との調整も神田明神や各町会が行います。その他には多くの方に関心を持っていただけるように、ガイドブックやウェブサイト、映像コンテンツなど広報物の制作から、イベントや外部とのコラボレーションなどの企画もしますね。
——神職のイメージからは想像つかないほど多岐に渡ることを担当されていますね…!
特に神田祭はアニメや漫画、スポーツ関連などコラボレーションの幅が広く、とても開かれているように感じます。
岸川 各町会でも独自でポスターをつくったり御神輿を展示したりと工夫して盛り上げている中で、神田明神だからこそできる発信を意識して取り組んでいます。例えばアニメとのコラボについては氏子区域に秋葉原が含まれていますし、神保町周辺もアニメの原作を扱う出版社が多いので親和性が高いんです。地域の特徴を活かしたコラボは、個性豊かな地域に囲まれた神田明神だからできることだと思いますね。
——他の神社では実現し得ないような一見突飛なコラボも、地域性を汲んでいるんですね。
岸川 特にアニメとのコラボは、はじめは反対の声もありましたが、徐々に地域に根付いていきました。とは言え、コラボする作品はなんでもいいというわけでなく、歴史的背景や思想などマッチする要素があるかを重視しています。今年コラボした『薬屋のひとりごと』は、神田明神が薬の神様を祀っているのでとても親和性がありました。作品への関心から神田祭への興味にうまく繋げられるよう、そういった文脈は意識していますね。
また、「若者をターゲットにしてアニメとコラボしているんですか?」と質問されることが多いですが、アニメに親しむ世代はいまや10代から60代まで幅広いんです。神社というのは常に多様な世代を受け入れてきた場所なので、時代の変化に応じて各世代の興味関心を捉えようと心がけています。
●「神田祭を行う」ということを変えない
——いろいろな要素を取り入れつつも、神田祭の軸として大事にされていることはありますか?
岸川 伝統というものは時代に応じて形が変わっていくものなので、神田祭も形式自体はさまざまな点が変わっています。例えば、地域外からはじめて参加する人が増えればマナーや安全の問題についてルールを整えなければなりません。ですが、基本的には「変えないということを念頭に置いた上で変えていく」という姿勢が非常に重要です。歴史に則った上で変えることはあっても、基本はいかに変えないでやるかということがお祭りにおいて目指すべきことだと思います。
——まち自体の変化もある中で、神田祭が変わらないようにされていることはあるのでしょうか。
岸川 まちが変わってしまうことは今に限った話ではなく、江戸時代から現在にかけてさまざまな変化がありますし、致し方ないことだと思っています。その中でも、「神田祭を行う」ということを変えないことが重要なのではないでしょうか。
そのためには事故を起こさないための細かな調整が不可欠です。お祭りはみんながみんな喜ぶというわけではなく、騒音や道路封鎖によって苦情が来ることもあります。それでも伝統として続けられる形を模索し続ける。変わらないということは続けるからこそできることだと思いますね。
——続けること自体もそう簡単なことではないと思います。
岸川 過疎化で受け継ぐ人がいなくなって自然淘汰されたり、時代が変わって形式が見直されたり、受け継いできたお祭りがなくなることは珍しくありませんからね。その点、神田祭は担ぎ手も多いし、関わる企業も多いのでとても恵まれているんです。その中で、今後も長く続けていくためには、もっと地域外の人にも知ってもらいたいですね。



——神田祭は神様と氏子の関係のお祭りということでしたが、外に開いていくことはどういった意味があるのでしょうか?
岸川 もちろん氏神氏子の関係性が大前提にはありますが、神田明神は昔から名所として地域外から訪れる方が多く、そうした方の存在も神社には欠かすことができません。お祭りも同様で、行う人と見る人の両方がとても重要だと思うんです。やはり見物人が多くいた方が担ぎ手も盛り上がりますし、お祭りとして活気が生まれる。地域外の人にもより関心を持ってもらうということは神田祭を今後も続けていく上で大事なことですね。
——氏子総代の廣瀬さんが「盛り上げるのはまちの人の役割」とおっしゃっていましたように、見る人も大事な盛り上げ役ということですね。本当に多くの方が関わるお祭りですが、改めて神田明神にとって神田祭はどういった存在でしょうか?
岸川 本来お祭りというものは神社の創建とともに行われます。神田祭の場合は創建当時の記録が残っていないため、どういった形で行われていたかはわかりませんが神社の歴史と密接に関わる存在です。だからこそ変えてはいけないし、続けていかなければならない。もちろん震災やコロナなどで中断した時期もありましたが、その都度復活させてきました。神田祭が続いているということは、まちの人も神社も活気を持ち続けているということでもあるので、「神田祭は、氏子のまちがあり続けている証」と言えるんじゃないかと思います。

〜〜〜〜〜〜〜
神田祭に限らず、あらゆる伝統の背景にはそれらを受け継いできた人々がいます。その一人ひとりについて語られることはそうありませんが、伝統が残っていることがそうした存在の確かな証拠です。
そんな中、今回お話を伺った三人が揃って大事にされていたのは「氏子であるまちの人に楽しんでもらう」ということ。まちの人を主役として、そのためにきめ細やかに尽力する様子はまさに陰の立役者だと言えます。
崇高な神事であり、神田を誇る伝統であり、まちの人の晴れ舞台である神田祭。参加者としては祭りの空気に身を任せて素直に楽しむことが一番の仕事ですが、陰で支える人たちの尽力に思いを馳せながら存分に楽しみたいと感じました。
Edit/Text: Akane Hayashi
Photo: Yuka Ikenoya(YUKAI)