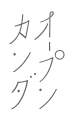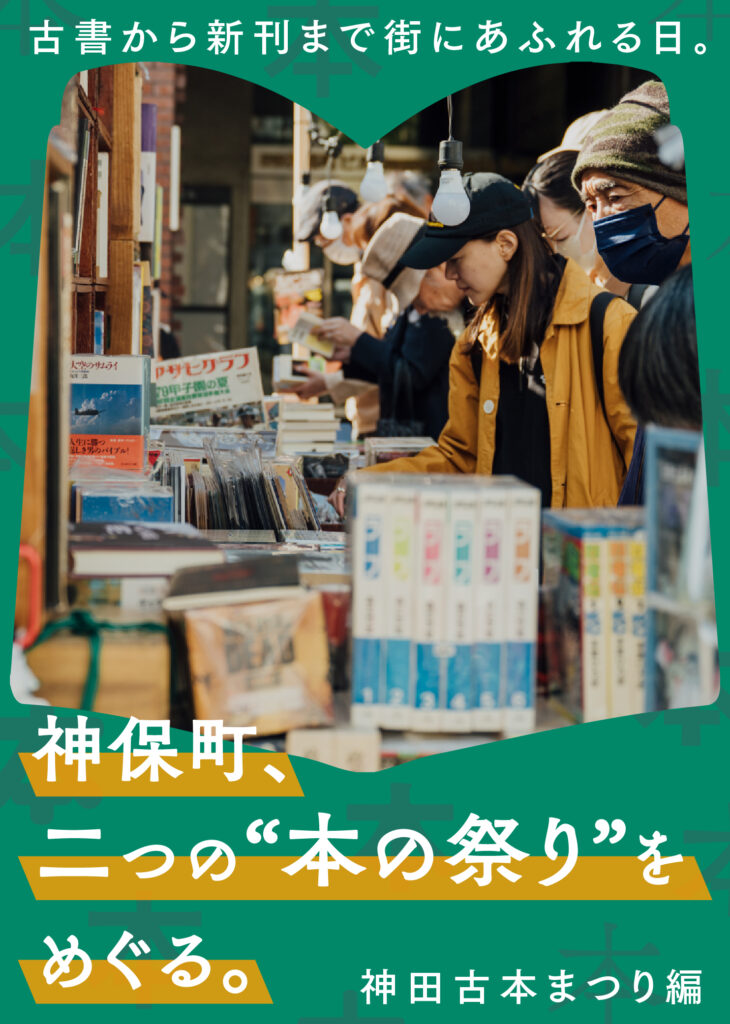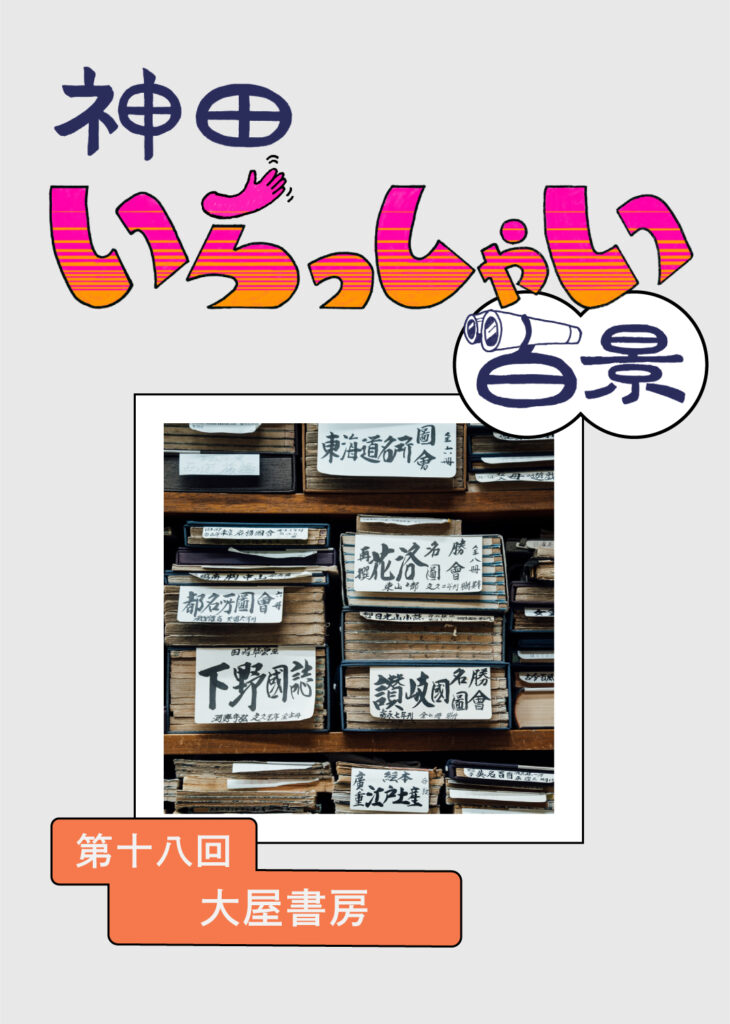神田祭、陰の立役者たち|其の二・氏子総代
日本三大祭のひとつとされる神田祭。
壮大な歴史と規模を誇る日本屈指のお祭りですが、そこには、まちの人々の手によって絶やすことなく受け継がれてきたという背景があります。時代とともに、地域に関わる人もまちの形も変わりゆく中で、伝統としてあり続ける神田祭。どういった人たちが、どのようにしてこの日を支えているのでしょうか。
約400年の歴史を持ち、108町会が参加するほどの規模ゆえに、関わる人の数も膨大ですが、その中で中心となって支え続ける「陰の立役者」に密着します。
二人目は、地域住民である氏子を代表する「氏子総代」。衆望のある氏子として選ばれ、地域や神田明神と細やかに関係を築き、まちの未来に向けた重要な判断を担います。
100以上の町会で構成される氏子地域をごく数人で背負う氏子総代。そのひとりである廣瀬直之さんにお話を伺いました。
〜〜〜〜〜〜〜〜
●地域の代表として神田がどうあるべきか

——「氏子総代」という言葉自体、あまり馴染みがない人も多いかと思います。まずはどういった役割をされているかお伺いできますか?
廣瀬 神様が守る地域に住む人を氏子と言い、その代表ということで「氏子総代」と呼ばれています。神田明神に対する崇敬心を強く持った地域の代表として、神田明神の宮司から直接任命されます。現在は神田から6名、日本橋から4名により構成されています。
主な役割は、神田明神と連携して祭礼や神社の保持活動を支えること。神田明神は大きな神社なので神職の数も多く、非常に重層的な組織となっていますが、その中で氏子総代のポジションは会社で言うところの「取締役」に近いかもしれません。神田明神で検討されるあらゆる執行に関して意思決定をする責任者という立場ですね。
——まさに企業のように役割が分かれているんですね。町会長とはどういった違いがあるのでしょうか?
廣瀬 神田祭の例で言うと、参加する町会は100を超え、さらに町会によって御神輿の管理や担ぎ手の数など状況が異なるので、実務的な部分は町会のことを一番把握している町会長が担います。
それに対して氏子総代は、神田祭自体をどういった方針や予算で実施するのか、神社の今後も見据えた理念的な判断に関わります。神田祭は地域のための伝統行事なので、検討の場には氏子が参加する必要がありますし、多様な知見や経験を踏まえて議論できる体制になっているんです。
——地域の代表として、まちの方とは普段どのようにコミュニケーションされているのでしょうか?
廣瀬 町会のお店に行ったり一緒に飲みに行ったり、息子が青年部に入っているので寄り合いに参加してさまざまな声を伺うようにしています。とはいえ、氏子総代になる以前からの付き合いの方も多いですし、なるべく日常の中で畏まらない形で接点を持てるようにしていますね。
——変わらない距離感でいることこそ、まちからの信頼につながっている気がします。神田祭当日は、氏子の方々は御神輿を担いで宮入を目指しますが、氏子総代の方はどういったことを担当されるのでしょうか?
廣瀬 神田祭は宮入の一日が本番だと思っている方も多くいらっしゃいますが、その前後6日間に渡ってさまざまな行程があるんです。大きなところで言うと、宮入の前日に神幸祭という大行列があり、神様に鳳輦(屋根に鳳凰を飾った御輿)にお乗りいただいて氏子地域を巡ってご祈祷をいただくもので、氏子総代も参列します。宮入とは別の日にも能の披露や献茶式があり、神様に対する御奉仕の儀礼として代々受け継がれている通りに執り行っています。氏子全員がすべてに参加することは難しいので、氏子の代表としてそれらを始まりから終わりまで見届けることが大きな役割かもしれませんね。


●氏子総代になって見えるまちの景色
——氏子の代表という立場にはかなり責任を伴うかと思いますが、氏子総代になられてから神田との関わりに変化はありましたか?
廣瀬 もともと父が氏子総代を長く務めていたこともあって神田とは長く関わりがありましたが、これを機に改めてまちの成り立ちを学び直しています。神社のことはもちろん、それを取り巻くまちの文化がどのように紡がれてきたのかを踏まえることは、氏子の代表として然るべき判断をするためにも大事だと思いますしね。他方で、まちの歴史を知らない方も増えてきているので、知っていただく機会もつくるようにしています。
——まち自体もさまざまな変化がありそうです。
廣瀬 そうですね。神田は多様な専門店街が集積する地域という特徴がありますが、その背景には歴史的に職人が多く行き来し、さまざまな専門分野において秀でた人が集まる地域だったからと言われています。さらに大学が集まるようになって古書店が増えたり、留学生の交流が始まったことでインド料理や中華料理が増えたりと、あらゆる歴史が現在のまちの姿に繋がっているんです。今後も再開発の計画があり、それに伴って神田祭にも影響があるかもしれません。ただ、まちが変わることはもはや当たり前なので、そういった背景を踏まえて神田らしい変わり方をしていきたいと思います。



——神田祭に対しても変化を感じることはありますか?
廣瀬 神田祭の内容自体はそこまで変わっていませんが、お祭りを取り巻く人は変わっているように感じます。住民の数は減ってきている一方で勤務されている方が非常に多く、そういった方々が伝統を受け継ぐ担い手として神田祭に参加してもらうことも増えてきました。ただ、外から来られた方はまた外に戻ってしまうので、より深くシンパシーを感じていただける工夫をしなければならないと思っています。
●次の世代に繋げるために必要なこと
——改めて、神田祭ほどの規模のことが当たり前のように行われているのは本当にすごいことだと思います。まちを大いに使って開かれていることで、地域の祭礼でありながら地域外の人も入り込みやすいように思います。
廣瀬 氏子総代としては、前に出るのではなく氏子の方々に楽しんでもらうことに徹している点が上手くいっているのかもしれませんね。町会には大いに盛り上がっていただいて、我々は現場の状況を見たり意見を吸い上げたりと、俯瞰的に地域を面として捉えてまとめる立場にいることが、こうした規模の行事には必要だと思います。
——俯瞰して見るというのはまさに取締役ですね。神田明神では神田祭以外にも多様な取り組みをされているので、氏子総代の活動も多岐に渡りそうです。
廣瀬 そうですね。例えば、神田明神の創建1300年記念事業として御社殿の大規模改修の計画がありますが、そういった方針の議論にも参加します。他にも日々の運営から初詣や季節ごとのお祓いなど、年間通してさまざまな取り組みの検討に関わっています。
——具体的にどのような検討をされるのでしょうか?
廣瀬 改修一つとっても、歴史的な建造物に手を加えるわけですから、どこをどういった方法で改修するかは非常に重要です。大幅改修するとなれば、当時の設計がどのようになされていたのか研究者の意見を伺うなど、理解を深めた上で改修の方針を慎重に判断します。単にお金をかければいいということでも合理的であればいいということでもなく、祈りの場である神社をどのように次の世代へ持続させられるかを軸に、一つひとつを議論しているんです。
——いま、次の世代に繋げるためにはどういったことが重要でしょうか?
廣瀬 お祭りには二面性があって、神様を祀っておもてなしをする神聖な面と、神様をもてなす場で地域の人も楽しんでしまう祝祭的な面があるんです。特に子どもの頃なんかは、祈りの場というより屋台がたくさん出ていて楽しかった記憶の方が強いですよね。でもそれが儀礼として続いていくための大事な要素です。
そうした時に氏子総代は、神聖な儀礼として執り行いつつも、まちのみなさんがいかに難しいことを考えずに楽しめるようにできるかが、次の世代に繋げるために重要だと思っています。



——確かに、実際に参加してみると厳かというよりもまちのみなさんの笑顔で溢れていたのがとても印象的でした。
廣瀬 もちろん大規模な行事なのでトラブルが起きないようさまざまなルールを設ける必要がありますが、定めすぎても窮屈になってしまうので、楽しめる場であることを一番に考えながら守るところは守るようにしています。例えば、屋台で焼きそばを買って食べることはもちろんいいけれど、拝殿の階段に座って食べることは著しく神域を穢す行為なので注意しないといけない。どこまで緩めてどこまで規制すべきかの線引きは常に悩ましいですが、まちのみなさんからの意見も伺いながら柔軟に判断するようにしています。
——歴史があればあるほど「変えない」という意識が強くなりそうですが、時代に適応しながらあるべき姿を考えていらっしゃるんですね。本当に難しく責任のある立場だと改めて感じます。
最後に、そういった立場の氏子総代として神田祭はどういった存在でしょうか?
廣瀬 「神田」という地名を掲げている通り、神田祭は一地域のお祭りではありますが、神田は江戸を代表するまちなので、日本を誇る存在と言っても過言ではないと思っています。まちの方々も神田祭に強く誇りを持っているので、そうした想いを最大限に引き出せるようにしていきたいですね。

Edit/Text: Akane Hayashi
Photo: Tada, Yuka Ikenoya(YUKAI)